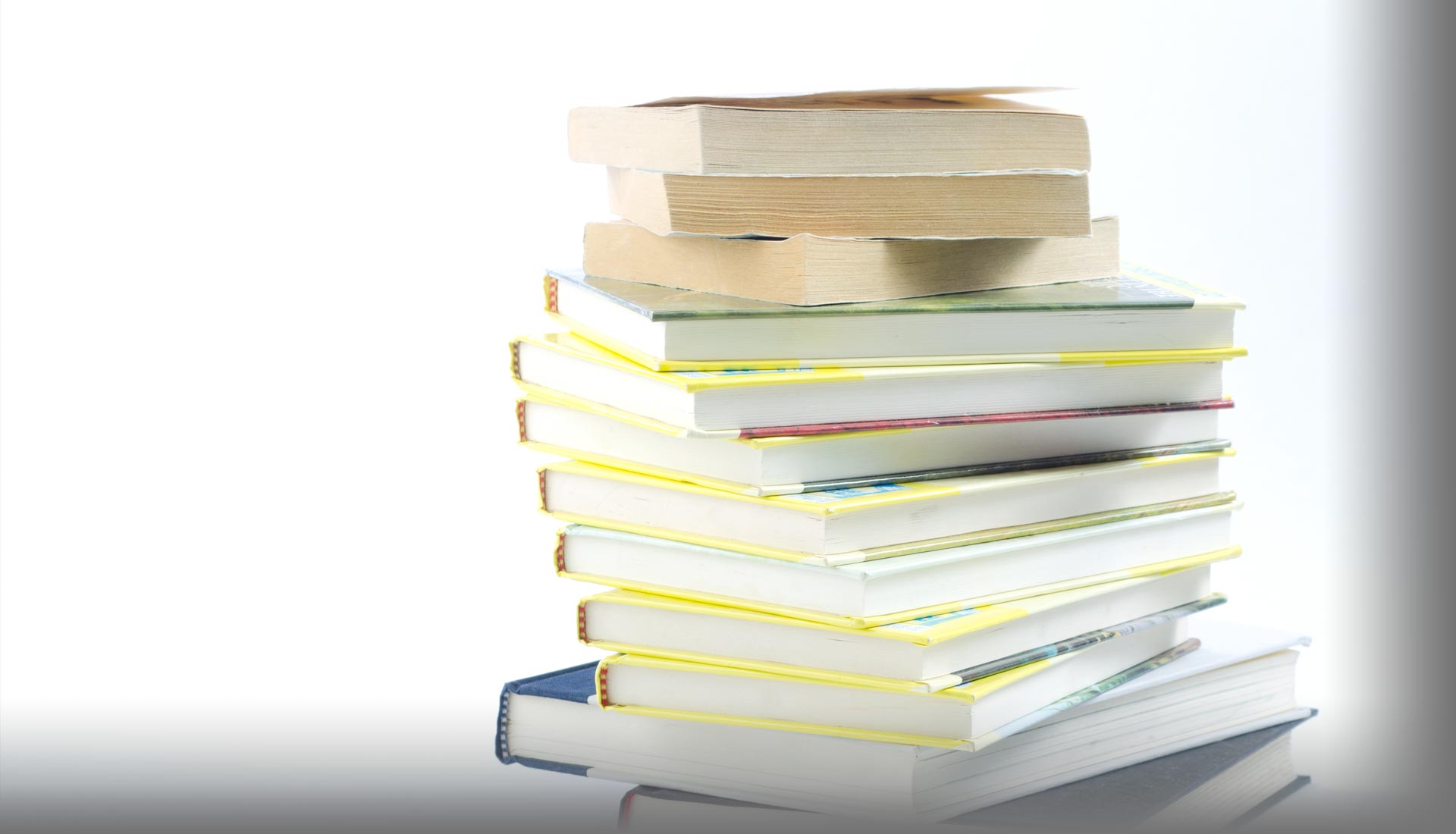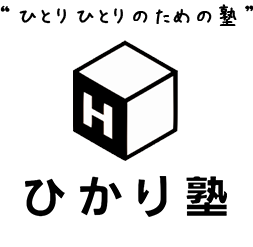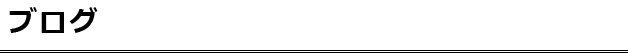なかみなと教室ブログ
自主学習で悩んでいる生徒に意識して欲しいこと
date.2025.05.23自主学習は、具体的に何をしていますか?
「教科書の内容をノートに写した」「ノートに単語をたくさん書いた」最近だと「動画を見た」もありますね。
時間をかけた、たくさん書いたということだけで評価しているとなかなか成績が伸び悩んでしまいます。
大切なのは「自分は何をどれだけ理解しているか?」を自分で把握していること。
質と量の話だとまずは量からというのはありますが、だからと言ってひたすらに量だけこなすのではなくある程度の質、ここは押さえておいてほしいです。
宿題や自主学習はやっているけどなかなか点数が伸びないなという方は次の2点を意識してみてください。
1. 勉強前に「目的」を書く
例:「今日は分数の約分をマスターする」
2. 勉強後すぐに「思い出す」
例:ノートや教科書を見ずに、何を学んだかを自分の言葉で書き出してみる
まず1点目。
勉強を始める前に目的をはっきりさせます。
そうすると次に「どこに注意して読むべきか?」「この動画のポイントは何か?」と力の入れどころが見えてきます。
最近は動画視聴での自学も増えてきましたね。中学生も自宅でYouTubeで見ていますし、高校生は学校から映像授業が与えられているところも増えてきました。図書館などでタブレット置いて動画見てる高校生たくさんいますね。
学習において気を付けたいのが受け身一辺倒にならないこと。
「読んで満足、聞いて満足」ではその学習内容はほとんど身についていないでしょう。
その学習を終えたあと、自分は何を獲得できたらいいのでしょうか。
その学習の目的をしっかりと定めましょう。
目的が定まれば、集中すべきところできちんと集中できます。
ここだ!というところに力を入れ、記憶に刻み込んでいきます。
これが要点をつかむってことですね。
そして2点目。
すぐに学習した内容を思い出してみてください。
何も見ずに自分の頭の中から学んだことを引っ張り出してみてください。
どうしても出てこないときは目次を見たり、ノートを少し見たりして思い出してみてもいいです。
思い出すことで脳に「これは重要な情報だ」と認識させる働きがあり、記憶の定着に非常に効果的です。
「社会が苦手」という生徒に話を聞くと教科書をよく読むことはしていますが、解く問題の量が圧倒的に少ないです。
インプットばかりをしていてアウトプットをしていません。
学習した内容を思い出す機会がないのです。
問題を解くというのも思い出すということなので、繰り返し問題を解くことが定着のカギになります。
この2点を意識して学習してもらえれば、定着しているという実感もすぐに得られると思います。
| date.2025.11.18 | その2 |
|---|---|
| date.2025.10.24 | 読書しない子どもが増えているらしい |
| date.2025.9.30 | 【9月のロボット】ロボットしょうぼうたい |
| date.2025.9.24 | 国勢調査 |
| date.2025.7.30 | 【お知らせ】津波警報 |